親が亡くなったあと、残された実家をどうするか…。
多くの人が直面するのが「家じまい」という問題です。
思い出の詰まった家を整理するのは、心情的にも大変な作業。
しかし、放置すると固定資産税の負担やトラブルの原因になることもあります。
この記事では、家じまいをする際の注意点や必ず行うべき手続き・作業を、わかりやすく解説します。
🪦 まずは「相続手続き」を確認しよう
家じまいの前に最初に行うべきは、不動産の相続手続きです。
👉 親名義のまま勝手に処分することはできません。
法的な所有者を確定させるために、遺産分割協議書の作成と登記の変更が必要です。
✅ 相続登記の基本手順
- 戸籍謄本・除籍謄本を取り寄せて相続人を確定
- 相続人全員で話し合い、家をどうするか決める(売却・解体・維持など)
- 遺産分割協議書を作成
- 不動産の名義変更登記を申請
💡 2024年4月から、相続登記は義務化されています。
放置すると過料(罰金)の対象になる可能性もあるため、早めの対応が大切です。
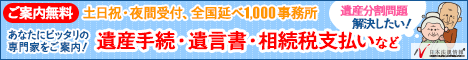
🧹 家の中の整理は「思い出」との向き合い方も大切に
家じまいで最も時間がかかるのが「遺品整理」です。
思い出の品を見つけるたびに手が止まってしまうものですが、
感情に流されず、計画的に進めることがポイントです。
🗂 遺品整理の進め方
- 貴重品や重要書類の確認(通帳・印鑑・保険証券・権利証など)
- 形見として残すものを家族で話し合い決定
- 不要なものは分別・処分(可燃、不燃、リサイクル)
- 業者に依頼する場合は複数見積もりを取る
💬【ワンポイント】
遺品整理業者の中には悪質な業者も存在します。
「遺品整理士」などの資格を持つ信頼できる業者を選びましょう。

💰 売却・解体・維持、それぞれのメリットと注意点
家じまいでは「家をどうするか」を決める必要があります。
🏘 売却する場合
- 固定資産税の負担がなくなる
- 現金化できるメリット
🔸注意:相続登記が完了していないと売却できません。

🧱 解体する場合
- 空き家による近隣トラブルを防げる
- 管理の手間がなくなる
🔸注意:解体費用は100万~300万円ほど。自治体の補助金制度を活用できる場合もあります。
🧺 維持する場合
- 思い出の家を残せる
- 将来的にリフォームや賃貸も可能
🔸注意:定期的な管理が必要(換気・清掃・郵便チェックなど)。
🏛 行政・公共手続きも忘れずに!
家を片付けるだけでなく、公共手続きも重要です。
📋 行うべき手続き一覧
- 電気・ガス・水道の解約
- NHKやインターネット契約の停止
- 固定資産税の名義変更
- 郵便物の転送手続き
🕊 また、故人名義の口座や保険の解約も早めに進めておきましょう。
手続きは死亡届の提出後、おおむね1か月以内に行うのが理想です。
👪 家族での話し合いが「もめごと防止」のカギ
家じまいは、感情がぶつかりやすい場面でもあります。
「思い出を捨てたくない」「維持したい」「早く売りたい」など、家族の意見が分かれることも。
🗣 トラブルを避けるために大切なのは「共有と合意」。
定期的に家族会議を開き、LINEやメールで経過を記録しておくと安心です。
📦 専門家に相談するのもおすすめ
すべてを自分たちで行うのは大変です。
最近では「家じまい代行サービス」や「空き家管理サービス」なども登場しています。
💼 相談先の例:
- 司法書士(相続登記)
- 税理士(相続税・譲渡所得)
- 不動産会社(売却・査定)
- 遺品整理業者(片付け・処分)
必要に応じて、複数の専門家に相談することでスムーズに進められます。
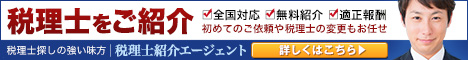


🌸 まとめ:感謝の気持ちで「家じまい」を
家じまいは、ただの片付けではなく、
親や家族の思い出を整理する心のセレモニーです。
無理をせず、家族や専門家の力を借りながら、
「ありがとう」という気持ちで一歩ずつ進めていきましょう。
🕊 家じまいは“心の整理”の第一歩。
大切な思い出を胸に、新しい暮らしへ前進していきましょう。

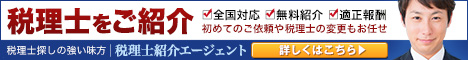
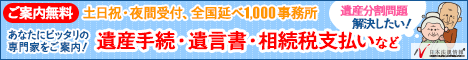


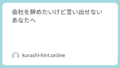

コメント